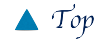📓 『カタカムナ』 全80首の意味−第68句の解説
『カタカムナ』第68句 前回に引き続き『生活の知恵・食べ物確保編』です。 前回の句で解説したのは『山菜採り』と〝ここから先は入ってはいけない〟という、人間界と自然界の境界線のお話でしたが、今回は『稲作・海の漁』の注意点を解説しています。 陸地と海、なぜ同時に警告してるのかというと?
『カタカムナ』第68句の解説
📓 【原文】
【漢字に直すと?】『カタカムナ』 第68首
トヨホ イホ カムナガラ…… オホカムカエシ ワケカエシ イキトキ オホワカエシ スベ ソラ カムナガラ…… オキハヒ オキナギ サキ アヤ オキツ アカユラハ ユタヘ
『カタカムナ』 第68首🔎 【この句の意味は?】
豊穂 稲穂 惟 神…… 大神返し 理由返し 生き時 大輪返し 術 空 惟 神…… 沖 灰 沖 凪 先 術 沖 津 赤揺らは 揺他へ
『カタカムナ』 第68首『カタカムナ』が降ろされた、蘆屋道満が住んでいた地域は、現在の兵庫県芦屋市あたりでした。 なので、神様の説明も、この地域に住む人々を想定して行われています。 注意深く見てると、神様は『陸の男』に対しては厳しい顔を見せることもあるモノの、『海の男』に対しては、やや甘い気がする。終始一貫して、親心。 なぜなのでしょうね? 以前の句『カタカムナ』第49句の解説にあったように、 神様から見ると、海の男の勇敢さは『無鉄砲さ』に見えてしまい、常にヒヤヒヤしながら見てるからでしょうか? 神様の解説が降りてくれば、疑問も解けるでしょうか? ・ ・稲穂の豊作について、神が言うことは…… 神様にお返しする(自然のバランスを元通りにさせる) そういう気持ちで毎年の稲作にあたることだ 理由を言おう! 自然が長く生きるのは、元のバランスに戻るから。 そのバランスが崩れたとき 自然は「水害」によってその土地の回復を図る。 海の漁についても、神が言うことは…… 海面が黒く、風が強いとき 海の男がとるべき行動 海面が赤かったり(瀬戸内海の赤潮)渦が大きい(鳴門の渦潮)ときは? 無理をせず、穏やかな場所で待機すること
常にヒヤヒヤしながら見てるからだ。 漁に出ていく者と、漁から帰ってくる者の数が一致しないからな。 陸ではソコまでではないだろう? だから、海の男に対しては、警告を送りたくなってしまう。それでも、帰ってこない者が後を絶たないが。 ・ ・ 『カタカムナ』の解説に移ろう。 句の前半は、稲作の注意点。 同じ土地で調子に乗って栽培し続けると、どんどん土地のエネルギーが衰えて、作物の育ちが悪くなってしまう。 なので毎年、稲の栽培をする土地は少しずつ場所を変えながら、自然に対して負担がかからないように、かんながらの精神で言う、〝神様にお返しする〟という意識で行うことが重要になる。 なぜなら、自然のサイクルが整っているときこそが、大地からエネルギーがあふれ、霊験あらたかな土地となるからだ。 この国は、元々『神気』の宿る土地なのだ。 人間の身体と同じく、波動、気の乱れ、ツボのようなものが自然の中にもあって、一カ所が狂うと、連鎖反応で他の所も次々と悪くなってしまう。
『カタカムナ』第68句・神様本人による解説
そのバランスが崩れたとき、自然界は『水害』で土地をリセットしようとする。神ではないぞ。自然界だぞ。大雨による川の氾濫で、その土地のエネルギーを元に戻そうとするのだ。 そこに暮らす人々にとっては、落ち込むほどの災害であろう。土地や家、蔵の備蓄が流されるのだから。 だからこそ、それを避けるために、土地の声を聞きながら、稲の栽培をする必要があるのだ。 ・ ・ 句の後半は、海の男への注意点だ。 行ったきり、帰ってこない……にならないようにな。 海面が黒く濁り、風が強いときは、海に出てはならぬ。 そのようなときは、自らの命を危険にさらすだけだ。 また、海面が赤いとき(瀬戸内海の赤潮)や、渦が大きい(鳴門の渦潮)ときは、無理をせず機を見るほうがいい。 海の男は責任感が強く、食べ物がないときは、焦る気持ちも分かるが、そういうときほど、行ったきり、帰ってこない……になってしまうものだ。 無理をして、危険を冒すからだ。『カタカムナ』 全80首の意味−第69句の解説